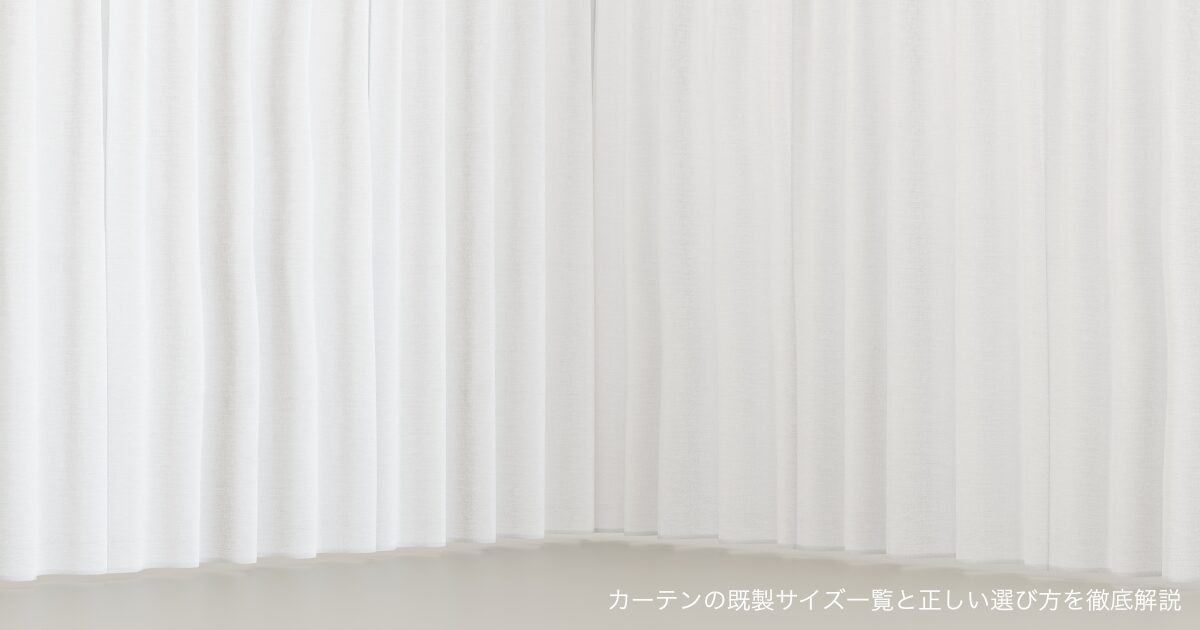カーテンを選ぶとき、「既製サイズで本当に合うのかな?」と不安になる方は多いのではないでしょうか。
既製カーテンは、手軽に購入できる反面、サイズ選びを間違えると見た目が悪くなったり、隙間ができたりと後悔することもあります。
そこで本記事では、代表的な既製カーテンのサイズ一覧をはじめ、掃き出し窓や腰高窓など窓のタイプ別に合った選び方、採寸のコツ、さらにサイズが合わないときの対応方法まで、わかりやすく解説します。
初めてカーテンを購入する方でも安心して選べるよう、具体例や注意点も交えて丁寧にまとめています。
サイズに迷ったときの判断基準も紹介していますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
【記事のポイント】
- 一般的な既製カーテンのサイズの種類
- 窓の種類ごとに適したカーテンサイズの選び方
- 採寸方法やサイズ調整の具体的な手段
カーテンの既製サイズ一覧と選び方の基本

一般的な既製カーテンの3サイズ
既製カーテンには、主に3つのサイズがよく使われています。これらは住宅に多い標準的な窓サイズに合わせて作られているため、購入しやすく、選びやすいという利点があります。
主なサイズは以下のとおりです。
- 幅100×丈135cm(腰高窓用)
- 幅100×丈178cm(標準的な掃き出し窓用)
- 幅100×丈200cm(ロング丈の掃き出し窓用)
この3つのサイズは、量販店やオンラインショップでもよく見かける定番サイズであり、多くの住宅に対応しています。
ただし、これらはあくまで「よくあるサイズ」であり、すべての窓にピッタリ合うとは限りません。
特に幅や丈が窓と微妙に合わない場合、カーテンの見た目が不自然になったり、光漏れの原因になることもあります。
このため、既製サイズを選ぶ前には、必ずカーテンレールの幅や床までの高さを採寸することが重要です。
また、カーテンは両開き・片開きのスタイルによっても必要な幅が変わってきます。
サイズに不安がある場合は、調整可能なアジャスターフック付きのカーテンを選ぶと、多少の差をカバーできるため安心です。
このように、既製サイズのカーテンは便利で手軽ですが、事前の採寸が欠かせません。
掃き出し窓と腰高窓のサイズ目安
カーテンを選ぶ際には、取り付ける窓の種類に応じたサイズ選びが大切です。特に「掃き出し窓」と「腰高窓」では、適した丈や幅が異なります。
掃き出し窓とは、床から天井に近い高さまである大きな窓で、ベランダや庭に出入りできることが多いタイプです。
このタイプの窓に合うカーテンの一般的なサイズは以下のとおりです。
- 幅100×丈178cm(標準的な掃き出し窓)
- 幅100×丈200cm(床と窓枠の高低差が少ないタイプ)
一方、腰高窓は壁の中間あたり、ちょうど腰の位置に設置される小さめの窓です。こちらには幅100×丈135cmのカーテンがよく使われます。
カーテン丈を決める際の注意点は以下の通りです。
- 掃き出し窓:レールから床までの高さから1~2cm引く
- 腰高窓:レールから窓枠下までの高さに15~20cm足す
この差は、カーテンが床に擦れることを防ぎつつ、見た目のバランスを保つためです。
ただし、窓の下に家具がある場合は、丈を短めに調整したほうが実用的です。
このように、窓の種類によって適したサイズは異なるため、用途や設置場所を考慮して選びましょう。
レースカーテンのサイズと特徴
レースカーテンは、光を取り入れながらも視線を遮る機能を持つため、日中のプライバシー保護や採光に非常に役立つアイテムです。
基本的にはドレープカーテンとセットで使われることが多く、サイズはドレープよりも若干短めに設計されています。
代表的なサイズの目安は以下の通りです。
- 幅100×丈133cm(腰高窓用)
- 幅100×丈176cm(掃き出し窓用)
- 幅100×丈198cm(ロングタイプの掃き出し窓用)
このように、レースカーテンはドレープよりも1~2cmほど短くなっているのが一般的です。これは裾が見た目に美しく収まり、汚れにくくなるためです。
また、レースカーテンにはさまざまな機能付きのタイプがあります。
- 遮像タイプ:外から中が見えにくく、防犯効果あり
- 遮熱・断熱タイプ:冷暖房効率を高める省エネ効果
- UVカットタイプ:家具や肌を紫外線から守る
ただし、遮像タイプは夜間に室内の照明がついていると効果が薄れることがあるため、完全な目隠しには不向きな場合もあります。
レースカーテンのサイズ選びは、ドレープとのバランスと、設置場所に応じた丈感がポイントです。機能面も含めて、自宅の環境に合ったものを選ぶと良いでしょう。
カーテンのサイズを正しく測る方法

幅はカーテンレールを基準に測る
カーテンの幅を決めるときに重要なのは、窓の幅ではなく「カーテンレールの長さ」を基準にすることです。
窓枠に合わせて測ってしまうと、必要な幅よりも短くなり、カーテンを閉じたときに隙間ができてしまうおそれがあります。
一般的な採寸方法は以下の通りです。
- 機能性レールの場合:両端の固定ランナーの間を測る
- 装飾レールの場合:キャップの内側から内側の長さを測る
この長さに対して、以下のように「ゆとり」を持たせてサイズを決めましょう。
- ドレープカーテン(1.5倍ヒダ):レールの長さ×1.05程度
- フラットカーテン:レールの長さ×1.1〜1.3程度
幅に余裕を持たせることで、ヒダの美しさが引き立ち、閉じたときにも隙間ができにくくなります。
一方で、幅を大きく取りすぎるとカーテンが重なりすぎて見た目が不自然になる可能性もあるため、最大でもレール長さの+15%程度に収めると安心です。
このように、幅の測り方はレールの種類とスタイルに応じて調整することが大切です。
丈は窓の種類ごとに測り方が違う
カーテンの丈を測る際は、窓の種類によって測る基準が異なります。
どの窓にも同じ測り方をしてしまうと、カーテンが長すぎたり短すぎたりして、見た目や使い勝手に影響します。
代表的な窓タイプと丈の測り方は次のとおりです。
- 掃き出し窓:ランナー下から床までを測り、そこから1〜2cm引く
- 腰高窓:ランナー下から窓枠下までを測り、そこに15〜20cm足す
- 出窓や出入り口のある窓:床に擦らないよう、床から1〜5cm短めに設定
このように測ることで、カーテンが床や窓台に当たるのを防ぎつつ、美しいシルエットを保つことができます。
ただし、窓の下に家具や棚がある場合は、カーテンの丈が干渉しないように短めに調整することが望ましいです。
また、アジャスターフックを使用することで、±4cm程度の丈調整が可能になります。
そのため、多少の誤差があっても微調整がしやすく、初めてカーテンを購入する方にも扱いやすい仕様です。
丈を正しく測ることは、快適な空間づくりにおいて見逃せないポイントです。
フックやレールのタイプに注意
カーテンの見た目や取り付け方に影響を与えるのが「フック」と「レール」のタイプです。
購入前にこれらを確認しておかないと、サイズが合わなかったり、思ったように取り付けられないというトラブルが起こりがちです。
フックには主に次の2種類があります。
- Aフック:レールが見えるタイプで、カーテンの上端がレールの下に位置する
- Bフック:レールを隠すタイプで、カーテンの上端がレールの上にかかる
取り付けたい見た目に合わせて、フックのタイプを選ぶことが大切です。
現在は多くの既製カーテンに「アジャスターフック」が採用されており、Aフック・Bフックどちらにも対応可能なものもあります。
また、レールにも種類があります。
- 機能性レール:シンプルでカーテンの開閉がしやすい
- 装飾レール:見た目が華やかでインテリアのアクセントになる
装飾レールの場合、レール端のキャップ部分が大きく、カーテンが端まで閉まりにくいことがあります。
そのため、レールの仕様に合わせてカーテンの幅やフック位置を調整する必要があります。
このように、フックとレールは単なる付属品ではなく、サイズ選びや使い心地に直結する重要な要素です。
購入前には必ず確認しておきましょう。
サイズが合わないときの対応方法

アジャスターフックで微調整する
カーテンの丈が少し合わない場合でも、アジャスターフックを使えば簡単に長さの微調整が可能です。
アジャスターフックとは、フック部分をスライドさせて高さを調整できる仕組みのもので、現在多くの既製カーテンに採用されています。
このフックを使えば、以下のような調整が可能になります。
- 約+1cm~−4cmの範囲で丈を微調整できる
- Aフック・Bフックどちらの取り付けにも対応できるタイプがある
- レールの見え方やカーテンの裾の位置を柔軟に変更できる
例えば、丈178cmのカーテンでも、アジャスターフックがあれば174cm程度まで短く調整できます。
これにより、床に擦れないようにしたり、見た目のバランスを整えたりといった細かい調整が自宅で手軽に行えます。
ただし、調整できる範囲には限界があるため、大幅に寸法が異なる窓には対応しきれません。
また、無理に調整しすぎるとカーテンの吊り下がり方が不自然になることもあるため、あくまで補助的な手段として利用するのが望ましいです。
サイズ選びに不安がある方は、アジャスターフック付きのカーテンを選ぶと失敗が少なくなります。
オーダーカーテンでぴったり調整
既製カーテンでは対応しきれないサイズの窓には、オーダーカーテンが最適です。
オーダーカーテンは、幅・丈ともに1cm単位で指定できるため、どんなサイズの窓にもぴったりと合わせることができます。
特に次のようなケースでおすすめです。
- 特殊なサイズの窓や大型の窓がある場合
- 出窓やコーナー窓など、既製品では形状が合わない場合
- 見た目や機能性にとことんこだわりたい場合
また、カーテンの柄や素材、遮光性などの機能も自由に選べるのがオーダーの魅力です。
一方で、納期が既製品よりも長くなることが多く、価格も高めになる点には注意が必要です。
しかし近年では、リーズナブルな価格帯で短納期に対応したオーダーカーテンも増えてきました。
採寸さえしっかり行えば、サイズも見た目も思い通りに仕上がるため、引っ越しや模様替えのタイミングには特に有効です。
ぴったりサイズを求める方は、オーダーを前向きに検討してみると良いでしょう。
丈直し無料などのサービスを活用
既製カーテンを購入したものの、丈が少し長い・短いと感じることはよくあります。
そんなときには、丈直し無料などのサービスを活用するのがおすすめです。
このサービスは、既製品のデザインや価格帯はそのままに、窓に合うよう長さを調整してもらえる便利な仕組みです。
主な特徴としては以下のような点が挙げられます。
- 製品購入時に指定した丈にカット・縫製してくれる
- 一部の店舗では最短当日出荷に対応している
- 幅直しにも対応している場合がある
特に、既製サイズで「あと少しだけ短くしたい」というケースでは、このサービスが大変役立ちます。
ただし、丈直し後の商品は基本的に返品や交換ができないことが多いため、注文前の採寸は慎重に行う必要があります。
また、商品によっては丈直し非対応のものもあるため、購入前にサービス内容をよく確認しておきましょう。
丈直し無料サービスを上手に使えば、既製品でもオーダーのようなフィット感を実現できます。
まとめ

カーテン選びで失敗しないためには、既製サイズの特徴や窓の種類に合った採寸方法を正しく理解しておくことが大切です。
既製カーテンでよく使われるサイズは「幅100×丈135cm」「幅100×丈178cm」「幅100×丈200cm」の3種類で、多くの住宅の窓に対応しています。
掃き出し窓や腰高窓といった窓の種類ごとに、最適なカーテンの丈は異なるため、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
- 掃き出し窓:床まで測って1〜2cm短め
- 腰高窓:窓枠下から15〜20cm長め
- レースカーテンはドレープよりも1〜2cm短めが一般的
また、幅は窓枠ではなくカーテンレールの長さを基準に測ることが基本です。
サイズが合わない場合でも、アジャスターフックや丈直し無料サービスを活用することで、微調整が可能です。
さらに、特殊なサイズの窓には1cm単位で指定できるオーダーカーテンが有効です。
これらの知識をもとに、自宅の窓にぴったり合うカーテンを選べば、見た目も使い勝手も満足のいく仕上がりになるでしょう。