遮光カーテンを購入したものの、「思っていたより暗くならなかった」「逆に暗すぎて困っている」などと後悔していませんか?
遮光カーテンは快適な暮らしをサポートしてくれる便利なアイテムですが、遮光等級やサイズ、色の選び方を間違えると、後悔につながりやすいのも事実です。
また、光漏れや設置方法によるトラブルも多く、思った通りの遮光効果を得られないケースも少なくありません。
そこでこの記事では、遮光カーテンで後悔しやすい具体的な理由やその対策、購入前に確認すべきポイントを分かりやすく解説します。
遮光カーテン選びで失敗したくない方、今のカーテンに不満がある方は、ぜひ最後までご覧ください。後悔のないカーテン選びのヒントがきっと見つかります。
【記事のポイント】
- 遮光カーテンで後悔しやすい具体的な理由
- 遮光性を高めるための工夫や対策方法
- 自分に合った遮光等級や選び方のポイント
遮光カーテンで後悔しやすい理由とは?
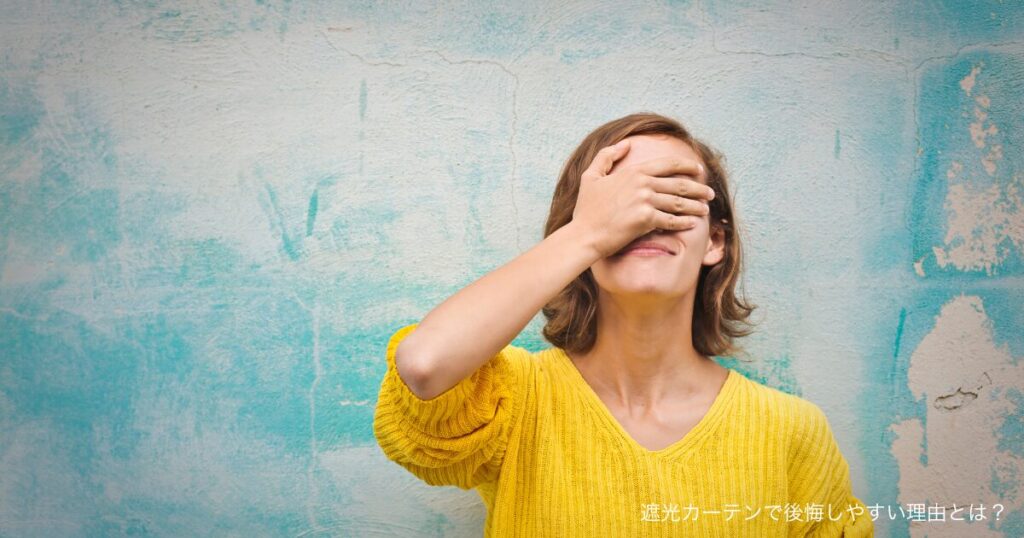
遮光等級の選び間違い
遮光カーテンの等級を正しく理解せずに選ぶと、期待通りの明るさにならず後悔するケースが少なくありません。遮光等級には「1級・2級・3級・完全遮光」があり、それぞれ光の遮り方に明確な違いがあります。
1級遮光は光を99.99%以上遮るレベルで、人の顔の表情が識別できないほどの暗さになります。完全遮光は生地自体の遮光率が100%で、より徹底して光を遮断します。
一方、2級や3級は遮光率が低く、柔らかく光を取り入れたい人向けです。しかし、これらを寝室に使ってしまうと「朝まぶしくて目が覚める」と感じる可能性があります。
選び間違いが起きやすいのは、以下のようなパターンです。
- 寝室用に明るめの2級を選んでしまった
- リビングに完全遮光を使い、日中でも薄暗くなってしまった
- 子ども部屋に3級を選んだら、逆に光が入りすぎて落ち着かない
こうした後悔を避けるためには、自分の生活スタイルやお部屋の用途に合わせて、適切な等級を選ぶことが大切です。
また、昼間にお部屋を暗くしたい方には完全遮光や1級が向いていますが、朝日を取り入れたい場合には2級や明るい色の1級遮光も選択肢となります。
光漏れの原因と見落としがちなポイント
遮光カーテンを選んだのに「思ったより明るい」と感じる原因の一つが“光漏れ”です。これはカーテン自体の性能ではなく、設置や環境に起因することが多いため、見落とされがちです。
特に気をつけたいポイントは以下の通りです。
- カーテンと窓枠の間にすき間がある
- 上部や両サイドから光が差し込む構造になっている
- カーテンサイズが窓に対して小さい
このような状態では、いくら遮光等級の高いカーテンを使っても、部屋全体がしっかり暗くなりません。
さらに、レールの種類や取り付け方も光漏れに影響します。例えば、カーテンレールにトップカバーがないと、上部からの光が入りやすくなります。また、両開きのカーテンの場合、中央部分に隙間ができてしまうこともあります。
こうした場合には、
- リターン加工でカーテンの両端を壁側まで覆う
- トップカバー付きのレールを使用する
- 窓サイズよりも一回り大きいカーテンを選ぶ
といった対策が効果的です。
見た目の美しさだけでなく、実用性を重視するなら「どこから光が入るか」にも注目して選ぶ必要があります。
デザインや色による遮光性の違い
遮光カーテンは同じ等級であっても、色やデザインによって遮光性の感じ方に差が生じます。特に初めて購入する人は、この点を見落としてしまうことが多く、後悔の原因になりやすいです。
一般的に、濃い色や暗めのトーンのカーテンは光を吸収しやすく、遮光性が高く感じられます。反対に、白やベージュなどの明るい色は光を反射しやすいため、同じ1級遮光でもやや明るく感じられる場合があります。
具体的には、
- 黒やネイビーなどのダークカラー:しっかりと暗く感じられる
- 白やアイボリーなどのライトカラー:柔らかい光がほんのり感じられる
- 柄入りや薄手の織りデザイン:デザイン部分からわずかに光が透けることも
このように、遮光等級だけを見て選ぶのではなく、色味や生地の質感、デザインの有無なども含めて選定することが重要です。
明るさの感じ方には個人差があるため、可能であれば事前に生地サンプルを取り寄せて、実際の見え方を確認してから決めるのがおすすめです。
遮光カーテン選びで失敗しないために

部屋ごとに遮光レベルを変える考え方
遮光カーテンは、すべての部屋に同じ等級を使う必要はありません。むしろ、部屋の役割や生活スタイルに合わせて遮光レベルを変えることで、快適な空間づくりが可能になります。
例えば、寝室はできるだけ暗くしたい場所です。睡眠の質を高めたい方や夜勤明けで昼間に寝る方には、1級遮光や完全遮光カーテンが向いています。外からの視線が気になる場合にも、防犯面で安心感があります。
一方、朝日で自然に目覚めたい方や、日中の光を適度に取り入れたい方には、2級または3級遮光がちょうど良い選択です。ほんのりと光を感じられるため、リビングや子ども部屋に適しています。
カーテンの遮光等級を部屋別に変える考え方のポイントは以下の通りです。
- 寝室:1級または完全遮光(安眠・防犯)
- リビング:2級または3級(自然光・明るさ重視)
- 子ども部屋:2級(朝日で目覚めやすい環境)
- 書斎やシアタールーム:1級(集中力維持・光の反射防止)
このように、部屋の用途を明確にして選ぶことで、遮光カーテンのメリットを最大限に活かすことができます。
実物サンプルや専門家の相談を活用
遮光カーテンを購入する前に、実物のサンプルを確認したり専門家へ相談したりすることは、後悔を減らすうえで非常に有効です。ネット通販では写真だけでは遮光性や生地感を正確に把握するのが難しいため、購入後に「思っていたのと違った」という声も少なくありません。
そこで役立つのが「生地サンプルの請求」です。多くのカーテン専門店では、無料または低価格で複数のサンプルを取り寄せることができます。自宅の光環境で確認すれば、遮光具合や色味の違いを実感できます。
また、インテリアコーディネーターやカーテン専門のプランナーに相談することで、以下のようなアドバイスを受けられます。
- 遮光等級の選び方(用途や方角に合わせた提案)
- カーテンサイズやレールの選定
- 好みのデザインと機能のバランス
特に新築やリフォーム直後の方、また遮光性に強いこだわりがある方には、事前相談がおすすめです。
こうした事前の確認やプロの意見を取り入れることで、自分に合った遮光カーテンをより正確に選ぶことができます。
サイズと設置方法で遮光性を高める
遮光カーテンの性能は、等級だけで決まるわけではありません。実際の遮光効果は、サイズの選び方や取り付け方法によって大きく左右されます。
まず、カーテンのサイズが小さいと、上下左右に隙間ができて光が漏れてしまいます。このとき、遮光率100%のカーテンを使っていても、お部屋全体は暗くなりません。
適切なサイズにするためには、以下の点に注意しましょう。
- 幅:カーテンレールの長さよりも左右5〜10cm程度長めにする
- 丈:床までの長さ+1〜2cmで、下からの光漏れを防ぐ
また、設置方法も重要です。カーテンを取り付ける際には、次のような工夫を取り入れると遮光性がさらに高まります。
- リターン仕様:カーテンの両端を壁に沿わせて隙間をカバー
- トップカバー付きレール:カーテン上部からの光漏れを防ぐ
- カーテンボックス:全体を囲うことで光を完全に遮断しやすくなる
特に寝室やシアタールームのように「真っ暗」に近い空間を求める場合には、サイズと設置方法にこだわることが効果的です。
見た目の美しさと機能性を両立させたい方こそ、これらのポイントをチェックしておくと安心です。
遮光性に不満がある時の対処法

遮光裏地やリターン加工で補う
遮光性が物足りないと感じたときに、カーテン本体を買い替えずに改善できる方法として「遮光裏地の追加」と「リターン加工」があります。これらは、既存のカーテンを活かしながら光漏れを防ぎたい方にとって、非常に有効な対策です。
遮光裏地とは、通常のカーテンの裏側に遮光効果のある布地を縫い付ける、またはフックで後付けするものです。遮光性を高めるだけでなく、断熱性や防音性も向上するというメリットがあります。
代表的な裏地の取り付け方法は次の通りです。
- オーダー時に裏地付き仕様を選ぶ
- 購入後にフックで簡単に取り付ける後付け裏地を使う
一方、リターン加工とは、カーテンの両端を壁に沿って折り返すように縫製し、サイドからの光漏れを防ぐ方法です。これにより、カーテンが窓をしっかり包み込み、遮光性が格段にアップします。
このような方法を活用すれば、気に入ったデザインを活かしつつ、機能性だけを強化することが可能です。遮光不足を感じた場合、まずは裏地や加工の追加を検討してみると良いでしょう。
カーテンとレースの併用で調整する
遮光カーテンの使い方として、厚地カーテンとレースカーテンを併用することで、遮光性や明るさを自在に調整することができます。とくに、朝と昼とで光の感じ方に違いがある場所では、この併用が非常に役立ちます。
基本的なスタイルは、窓側にレースカーテン、室内側に遮光カーテンを設置する「ダブルレール仕様」です。これにより、以下のような使い分けができます。
- 昼間:レースカーテンのみで自然光を取り入れる
- 夜間:遮光カーテンを閉じて光を遮る
- 休日の朝:状況に応じて明るさを調整
また、レースカーテン自体にも「遮像」や「UVカット」などの機能があるタイプを選べば、昼間のプライバシー保護や紫外線対策にも効果があります。
さらに、光をやわらげたい場合は、厚手のレースや柄入りのレースカーテンを選ぶと、遮光カーテンだけよりも自然で柔らかな印象になります。
このように、2枚のカーテンを上手に使い分けることで、過剰な暗さや明るさの悩みを軽減しながら、快適な室内環境を実現できます。
買い替え前に確認すべきチェックポイント
遮光カーテンが思ったより明るい、あるいは暗すぎると感じた場合でも、すぐに買い替えを検討するのは少し早いかもしれません。まずは、現状の問題点を正確に把握し、対策できる部分がないかを確認しましょう。
以下の項目は、買い替えの前にチェックしておきたいポイントです。
- カーテンのサイズは窓より十分に大きいか
- 窓枠上部や両端に隙間ができていないか
- カーテンの色や生地の厚さが遮光性に合っているか
- 使用しているレールが遮光に適したものか
- 部屋の用途に対して遮光等級が過剰または不足していないか
また、照明や外の光源(街灯など)が原因で明るく感じている場合もあります。このときは、遮光カーテンを交換しても根本的な解決にならない可能性があります。
さらに、前述の通り遮光裏地の追加やリターン加工などで対処できるケースも多く見られます。必要であれば専門スタッフに相談し、費用対効果のバランスを考えて判断すると安心です。
買い替えをする前に、こうした点を確認することで、不要な出費を抑え、より満足度の高いカーテン選びが可能になります。
まとめ

遮光カーテンを選ぶ際には、単に「暗くなるかどうか」だけで判断するのではなく、遮光等級・設置方法・カーテンの色やデザインといった多角的な視点が必要です。
後悔しやすいポイントとしては、遮光等級の選び間違い、設置による光漏れ、そして色味やデザインによる遮光性の違いが挙げられます。
そのため、次のような点を意識すると安心です。
- 部屋ごとに適切な遮光等級を選ぶ(寝室は1級以上、リビングは2〜3級など)
- サイズは窓より大きめに、設置はリターン加工やカーテンボックスで工夫
- 色や素材による光の透け方も確認し、必要なら生地サンプルを取り寄せる
- 遮光性が物足りない場合は、遮光裏地の追加やレースとの併用で調整
買い替えを急がず、まずは現状の改善方法を検討することで、納得のいく選択がしやすくなります。
遮光カーテンは、快適な暮らしを支える大切なインテリアのひとつです。ぜひご自身の生活スタイルに合った一枚を見つけてください。

